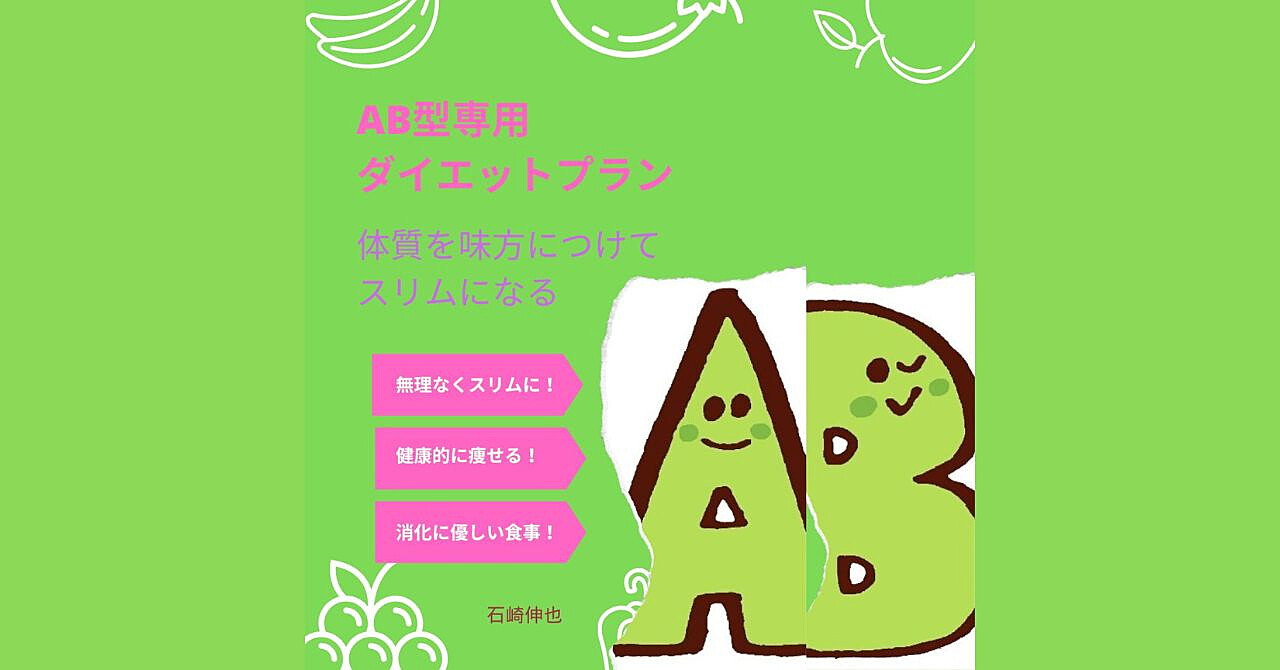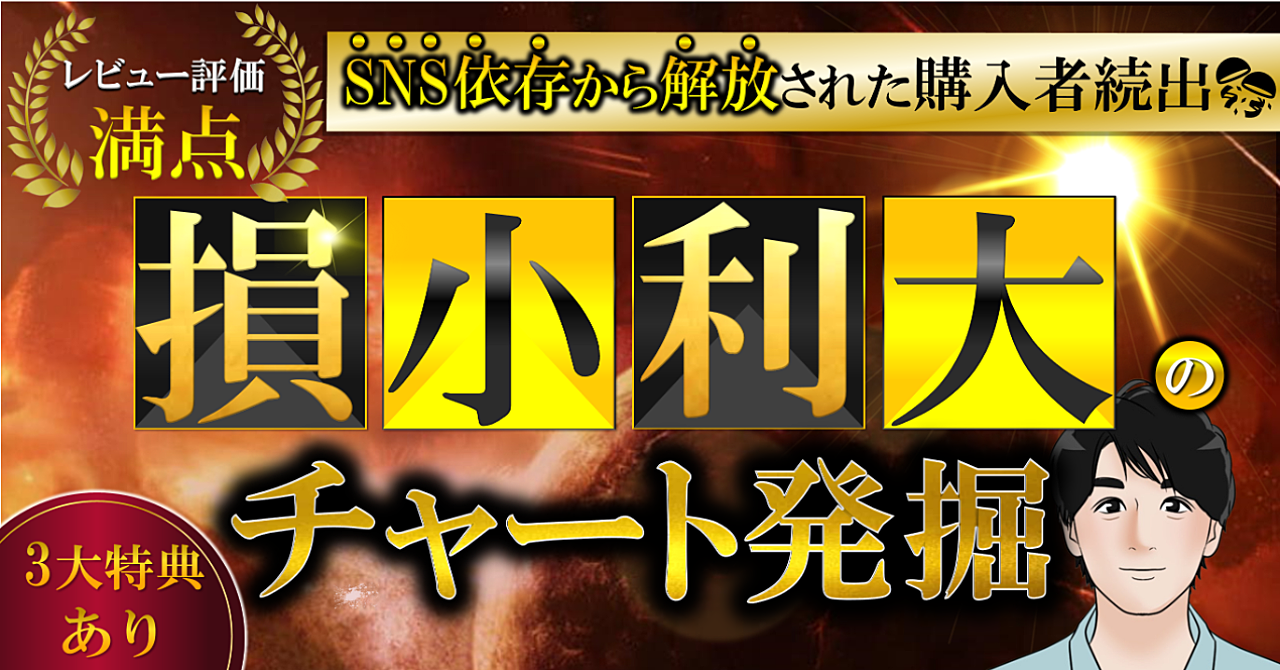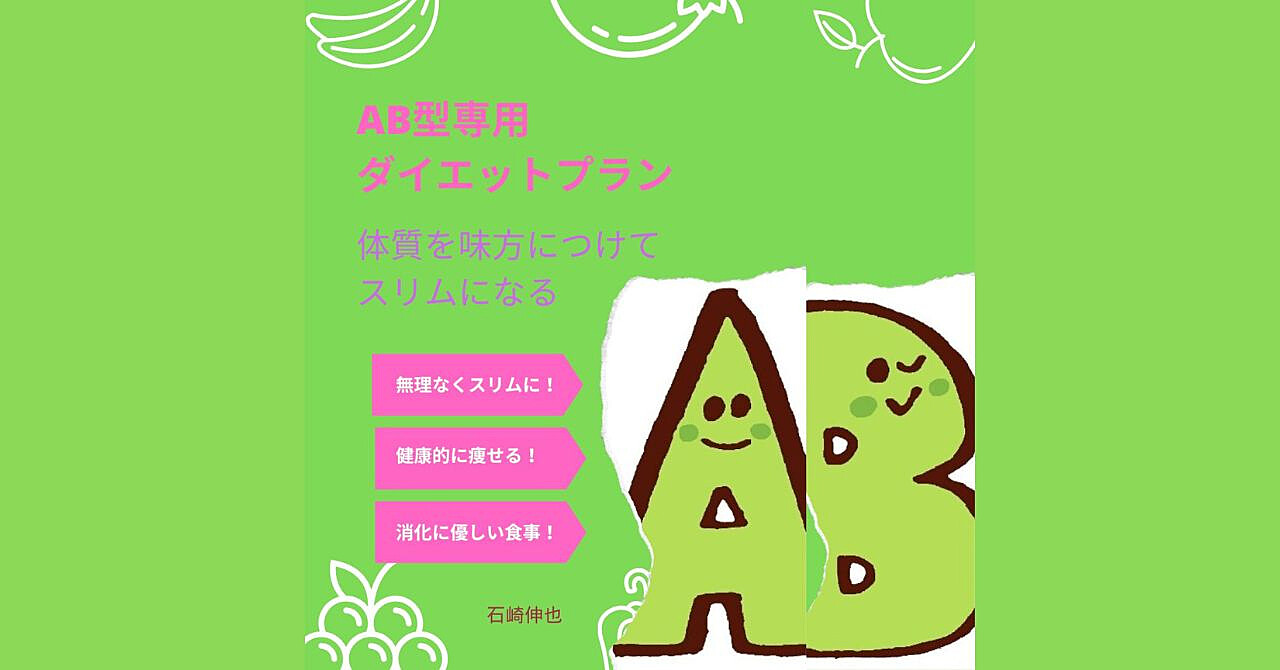
AB型専用ダイエットプラン
0 件のレビューがあります
平均スコア 0.0
前書きダイエットに取り組む際、多くの人はカロリー計算や運動量の調整に注目します。しかし、同じ食事や運動をしていても、痩せやすい人とそうでない人がいるのはなぜでしょうか? その鍵を握るのが「血液型」です。血液型と体質の関係に注目したダイエット法は、近年、科学的にも注目され始めていま
この記事のレビュー
0 件のレビューがあります
平均スコア 0.0